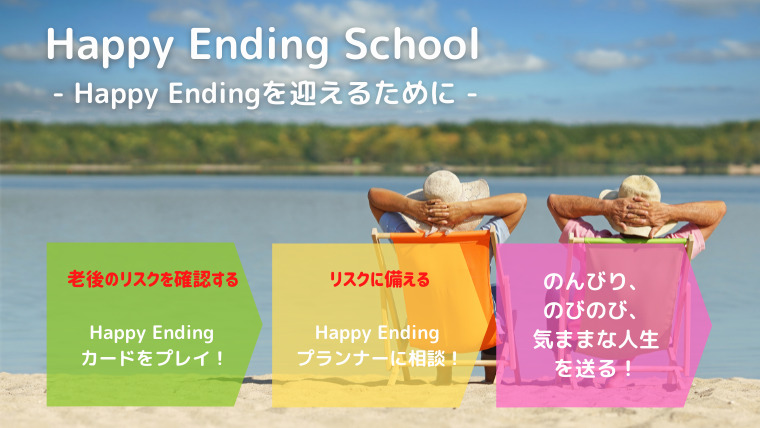ライフプランニング?!
生命保険に加入する前にセールスパーソンからやってもらいませんでしたか?
しかし、その後綺麗に印刷されたライフプランニングのシートを見返したことがあるでしょうか?
残念ながらせっかくのライフプランを時々見返しながら、あるいは見直しながら実行している人は、ほんのわずかであるようです。
ビジネスにおいては、PDCAのサイクルを回すことを重視しておきながら、プライベートにおいては「P」だけで終わってしまうのはなぜでしょう?
ロングタームを対象とするライフプランニングの限界を考えると、むしろダイレクトにオールリスクマネジメントを行う方が、精神的に豊かな人生を送ることができます。
オールリスクマネジメントとは、保険+”もうひとつの保険”です。
ライフプランニングとは

ライフプランニングは次の3Stepで行います。
ライフイベント(狭義のライフプラニング)の作成→ファイナンシャルプランニング→リスクマネジメント
<1>ライフイベント(狭義のライフプランニング)
まず、今後の人生において何(イベント)をしたいかをリストアップします。結婚、出産、教育、住宅、車、趣味、老後の生活資金などが中心となります。この際、実現可能性は考慮しません。
<2>ファイナンシャルプランニング
次に、作成したライフイベントの実行に必要な費用(支出)と得るべき収入をキャッシュフロー表に入力して計算し、実現可能性をシミュレーションします。
縦軸に収入と支出を取り、横軸に時間軸(年単位)をとります。そして、縦軸の上段に収入を、下段に先ほど考えたそれぞれのライフイベントにどれぐらいの費用がかかるかを見積って入力します。収入から支出を控除して、前年の貯蓄残高に加えると、最下段に累計の貯蓄残高が計算できるわけです。貯蓄残高がプラスの傾向が続けば実現可能なプランですが、赤字になるようであるならば収入を増やすか支出を削減するかどちらかの対処が必要であることがわかります。
キャッシュフロー表は日本FP協会のサイトで作ることができます。
お試しください。
<3>リスクマネジメント
最後に、病気や事故等で思わぬ出費の発生と収入がファインナンシャルプラン通りに入ってこない場合に備えて、保険を手当します。これがリスクマネジメントです。
以上の3Stepによって、人生の目標と資金的な裏付けと想定外の事態に備える保険の用意ができたことになるのですが、このライフプランニングのスキームに潜む問題点についてこの後に指摘します。
ファイナンシャルプランナー(FP)とライフプランニング
ライフプランニングを行うのはファイナンシャルプランナーですが、ファイナンシャルプランナーは、もともと生命保険を販売するために開発されたスキルなのです。
生命保険会社によっては自社のセールスパーソンをライフプランナーとか、ライフアドバイザーとか、ライフカウンセラーと称しているのは、ライフプランニングのお手伝いをしますよという意思表示なのですね。そして、彼等はすべてファイナンシャルプランナーの資格を有しています。
ライフプランニングの効用
主な効用は以下の3点です。
<1>今まで考えていなかった将来のことを、ライフプランニングを通じて、大まかに考えることができる。
<2>ライフプランの実現に必要な資金を把握することができる。そして、ライフプランの実現可能性を収入と支出、貯金残高の視点から総合的に判断することができる。
<3>作成したファイナンシャルプランニングを阻害するリスクを知って、ヘッジしたいリスクに対して、保険を手当して事前に備えておくことができる。
ライフプランニングをFPに依頼する。
FP(生命保険のセールスパーソンも)に依頼するメリットは以下の2点です。
1.依頼すると、ライフプランニングをせざるを得なくなる。
2.プランニングにFPの知識を活用できる。
3.FPのライフプランニングを行うソフトウエアを活用することができる。
4.客観的な提案を受けることができる。
生命保険のセールスパーソンのメリット
生命保険を募集する側のメリットも理解しておきましょう。
<1>見込客にアプローチする有効なきっかけとすることができる。
<2>保険にライフプランニングというオマケを付けることができる。
<3>ライフプランニングを通じて、提案する保険に必要な情報を入手することができる。
<4>ライフプランニングのプロセスを通じて、見込客と親しくなることができる。
ライフプランニングは生命保険のセールスパーソンにとって、見込客からプライバシーにかかわる情報を気兼ねなく聞き出すことができる「魔法の杖」のようなものだと言えます。
ライフプランが実行されない理由
冒頭に書いた通り、多くの人は、せっかく作成したライフプランを、保険契約時の参考資料としか活用しない残念な理由は、次の通りです。
<1>本人が、ライフプランの内容に納得感が持てず、その通りに実行するメリットを感じない。
自身と家族のセンシティブな情報を、生保のセールスパーソンに正直に包み隠さず申告する見込客は、多くはありません。
収入については、かさ上げした数字を申告する場合があるでしょうし、それまで、考えたこともなかったライフイベントについて突然問われても、付け焼き刃な答えしかできません。
子どもの進学とか、住宅の購入予定などについても確信があって申告したわけでもないライフイベントに対する自身の納得感も低くならざるを得ないのです。
その結果できたライフプランが綺麗に印刷されて見せられても、保険金額の根拠程度にしかならないのは仕方がないかもしれません。
<2>ライフプラン通りに行くはずはないと思っている。

いい大人であれば、今までの人生が必ずしも思った通りに行かなかったことを経験済みですから、今後数十年にわたるロングタームのライフプランがそのまま実現するはずはないと考えるのは、むしろ当然のことだと思われます。
皮肉なことに、厳密に作れば作るほど、ライフプランは現実から乖離していきます。
<3>ライフプランを忘れてしまう。
ライフプランに限らず、PDCAはすべてそうですが、Plan止まりで終わる理由は、第三者からのCheckが行われないためです。
ビジネスでは組織内でフォローする仕組みがありますが、あなたにライフプランを提案したセールスパーソンはその後フォローしてくれているでしょうか?
注意すべき見落とされているライフイベント
本人とセールスパーソンが気づいていない、あるいは意図的に対象から外してしまうライフイベントがあると、信憑性に欠けるカタチだけのライフプランとなってしまいます。FPの指導するライフプランニングに欠けている点を自分で補う必要があります。
<1>想定外(想定したくない)のこと
ライフイベントに盛り込むのは、結婚、出産、子育て、住宅、クルマ、旅行、趣味など前向きにできたらよいことばかりです。
想定したくない後ろ向きなライフイベントは、生活習慣病の発病、うつ病の罹患、失業、離婚、家族の不和等様々考えられますが、プランニング時点では想定できません。結果として上手く行った場合のライフイベントだけを並べることになります。
ライフプランニングでは想定外への対応は、3Stepめのリスクマネジメントの役割です。しかし、ここが問題なのですが、様々なリスクがあるものの、このリスクマネジメントでは保険でカバーできるリスク以外は無視されます。なぜならば、対応不能として、はじめから検討の対象外にしてしまっているのです。
失業や離婚、家族の不和などは保険で救うことができません。リスクとして別途管理する必要があります。
<2>親のことが、ライフプランニングの対象外になっている
ライフプランニングにおける落とし穴とも言える問題です。
一般的なライフプランニングの対象は、本人と配偶者と子どもまでです。何か足りないものがあると思いませんか。
それは両親のことです。人生100年時代は長生きする親と長く付き合うことになります。90歳の親を70歳の子と50歳の孫が面倒を見るのは珍しい光景ではありません。長寿化に伴って、子は高齢化した親の面倒を長く見ることになります。
そこには、多くの手間と時間とお金がかかるはずですが、それがライフイベントに入っていないのは片手落ちというよりは、むしろ誤ったライフプランであると言えるでしょう。親の介護の資金をキャッシュフロー表に入れる必要の要否も、考えておく必要があります。
人生100年時代の実態に合わないライフプランが提案される理由
1.ライフプランニングの目的は生命保険販売であること。生命保険に加入できない高齢者は検討の対象外です。
2.3Stepめのリスクマネジメントの目的が保険販売であるため、保険でカバーできないリスクは検討の対象外です。
生命保険販売を目的としたライフプランニングは超高齢社会に必ずしも適合しなくなっていると言えます。
風まかせの人生に必要なオールリスクマネジメント
ライフプランがお蔵入りする理由、意図的に見落とされるライフイベント、不完全なリスクマネジメントについて触れてきました。
ロングタームのライフプランは、所詮おおよそなのです。人生の海図にはなりえません。しかし、一度やってみることをおすすめします。たとえ一時的であったとしても、足下をしっかり見つめて、将来のことを考えるだけでも意味があります。
そうは言っても、海図もコンパスない人生の航海では不安でしょう。これからの時代に必要なのは、実現可能性の低い演繹的なライフプランに代わるシンプルな備えなのです。
我々の人生も、振り返って見ると、大航海時代の帆船のように風まかせではなかったでしょうか。強烈な逆風を上ろうとしても、結果として風に流されていくことが少なくありません。当初の目的は時の流れとともに変更されるのです。それを「風まかせ」だと言いましょう。
◇東京大学に入学したいと思っても、落ちてしまえば、浪人して再受験するか、受かった私立大学の選択になりますが、浪人を避けて私立大学にいくことを選ぶかもしれません。
◇野球が好きでプロ野球選手になりたかったが、そこまでの実績が上がらず、調理師になる人もいるでしょう。
◇熱烈に恋した恋人から振られて別の相手と結婚した人もいるでしょう。
しかし、それらの風まかせが、結果オーライであれば、それはよいではないですか。結果を見ると、計画(ライフプラン)通りがよいとは限りません。
人生は当初の計画通りに直線的に進むような単純なものではなく、風まかせの航海のように行ったり来たりと、遠回りしながら歩むものであることを我々はすでに経験済みです。当初の計画の策定とその実行にこだわるより、遠回りしても難破しないようにしておけば、次のチャンスはあるのです。
このように考えると、ライフプランニングの考え方である。ライフイベント→ファイナンシャルプランニング→リスクマネジメントという順番で考える必要がないことがわかります。
むしろ、少なくとも暗礁などに乗り上げないように、リスクの所在を把握して、備えた上で、風まかせに生きるのがシンプルで心地よいのではないでしょうか。
リスクマネジメントだけしっかりやっておけばよいのです。しかし、そのリスクマネジメントは保険だけでなく、もれなくオールリスクに対して行っておく必要があります。
保険でカバーできるリスクはごく一部
ライフプランニングにおける第3のステップであるリスクマネジメントの問題点は、カバーすべきと説明されるリスクの範囲が、保険でカバーできる範囲のリスクに限定されていることです。なぜならば、そのリスクマネジメントの目的がセールスパーソンの保険を売ることだからです。
生命保険のセールスパーソンが提案するリスクマネジメントは、生命保険でカバーできる範囲のリスクに限られるでしょう。ライフイベントをカバーするには火災保険、賠償責任保険、自動車保険等の損害保険も不可欠ですが、そこは対象外なのです。
しかし、少し考えてみるとわかるように、あなたを難破させるリスクは、保険事故だけではありません。人生の3大不安は、お金、健康、家族と言われていますが、生命保険、損害保険でカバーできるのは、お金の問題の一部に過ぎません。
しかも、必要な保険には生命保険と損害保険があり、両方に通じている保険募集人はごくわずかしかいません。そう考えると、あなたが行っているつもりのリスクマネジメントは、リスク全体のどのくらいをカバーしているのでしょうか?

(上の図で水色の部分が一般的なライフプランニングにおけるリスクマネジメントではカバーされない部分)
健康の問題、家族等の社会性の問題、住居の問題、法律上の問題、気持ちの問題等は、人生において大きなリスクとなりますが、ライフプランニングにおける一般的なリスクマネジメントにはそれが含まれていません。保険会社の保険でカバーできないリスクをカバーする”もうひとつの保険”が必要です。
人生100年時代に必要なシンプルで包括的なオールリスクマネジメント
◇ ”もうひとつの保険”を含めたオールリスクのリスクマネジメントをしておけば、余裕をもって自分の生きたい(風まかせの)人生を生きることができる。
◇ そのためには、専門家任せにせず、自分自身が、”もうひとつの保険”を含めて自分自身に必要なオールリスクマネジメントを浅くてもよいので広く把握しておく必要がある。
◇ 必要な ”もうひとつの保険”はシロウトでもHappy Ending カードをプレイすれば理解できる。
”もうひとつの保険”の必要性に気づくHappy Ending カード
まず、保険でカバーできるリスクをしっかり理解して要否を判断して必要なリスクには保険を掛けておきましょう。そして、そして、保険会社の保険でカバーできないリスクに対する保険が”もうひとつの保険”です。”もうひとつの保険”は保険会社の保険ではありません。
保険+”もうひとつの保険”ではじめてオールリスクマネジメントとなるのです。
Happy Ending カードは”もうひとつの保険”がカバーするリスクを知るためのカードゲームです。
Happy Ending カードでオールリスクマネジメントを一度お試しください。
早く知ってよかったと喜んでいただけると思います。
<プライベートユースの場合>
Happy Ending プランナーとプレイする → Happy Ending プランナー
ウエビナー(Happy Ending School)オンラインで受講する → Happy Ending カード体験会

<ビジネスユースの場合>
Happy Ending プランナー養成講座(リアルコース)
Happy Ending プランナー養成講座(ウエビナーコース)