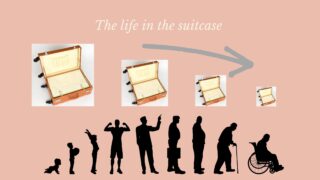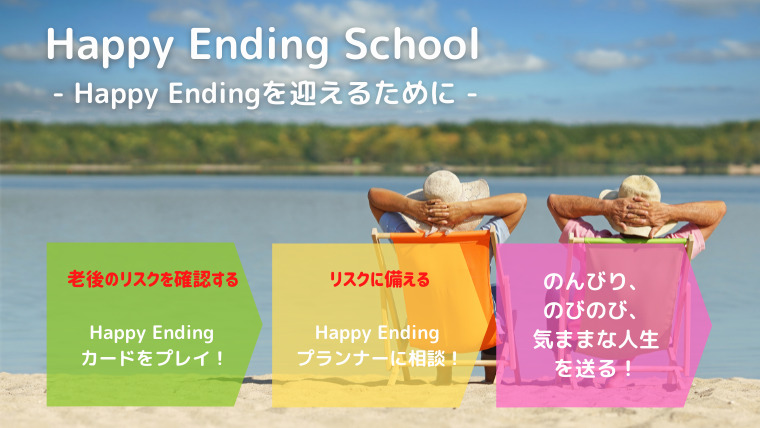認知症になりたい人はいないでしょうが、かと言って、そうならないために、なんらかの予防策を講じている人は多くはありません。
と言うのも、認知症になる原因を理解していなければ、予防のしようがありませんから……
日本では知られていませんが、デヴィッド・スノウドン教授らが行った有名な”nun study(修道女研究)”を知れば、あなたも認知症の予防を始めたいと思うのではないでしょうか。

ナンスタディ(nun study)とは
人生100年時代はいいことばかりではありません。長寿は健康であってこそめでたいことですが、認知症を患って長生きすることは必ずしも喜ばれません。
認知症予防とそのための原因究明は、人類の最重要課題のひとつです。
アルツハイマー病の原因を突き止めたいと考えていた疫学者のスノウドン教授らは、修道院で生活する修道女(nun)たちに着目しました。
修道女たちは、ほぼ18歳で修道院に入りますが、その後、生涯独身を通し、同じような仕事と同じ収入、同じ食事、煙草を吸わず、さらには受けられる医療も含めて、ほぼ同じ環境で生活します。その結果、他にはあり得ない均質な環境において個々人を比較できるため、修道女たちは疫学研究にうってつけなのです。
「100歳の美しい脳」デヴィット・スノウドン著 藤井留美訳 (株)DHC より
スノウドンのセレンディピティ
ある日、研究に協力してくれているノートルダム教育女子修道会の修道院を歩いていたスノウドンは、保管庫の部屋の存在に気づきます。その保管庫には所属する修道女全員の以下のデータが保存されていました。疫学研究者にとって、こうした記録に出会う事は、考古学者が未発掘の墓所を発見したようなものだったのです。
・ハイスクールの成績証明書
・写真
・自分で書いた半生記(22歳の時)
・シスターの子供時代から晩年までの詳細な記録
・死亡記録
ジム・モーティマーの「ブレイン・リザーブ」
この保管庫の記録が縁となり、スノウドンは老人医学の研究者であるジム・モーティマーとともに、彼の「ブレイン・リザーブ」仮説の検証を修道女たちと行ったのです。
「ブレイン・リザーブ」仮説
胎児期から思春期に至るまでの脳の発達の具合によって、強い脳と弱い脳ができる。
強い脳は基礎体力がしっかりしているので、アルツハイマー病になって組織がやられても、症状が出ない。
可塑性の高い柔軟な脳は、一部の組織が病気でだめになっても、神経細胞が新しい接続を創り出して機能を維持することができる。
ノートルダム教育修道女会の協力
研究の主旨と下記3点の協力を修道女たちに依頼すると、その内容の厳しさにもかかわらず、彼女達の多くが賛同し、協力を約束してくれました。
その結果、ナンスタディはプログラムの対象者1027名中678名が参加する大規模なスタディとなったのです。本書が出版された時点で修道女の脳の解剖は300例に及びました。
<1>修道院に保管されている修道女の個人記録や利用記録を提供すること
<2>年1回、身体能力と精神能力の詳しい検査を受けること
<3>死後、脳を取り出して解剖すること
スライスされた脳を調べてわかったこと
アルツハイマー病に冒された脳の二大特徴は、神経原線維変化とプラーク(アミロイドβ)の存在です。

(脳神経のイメージ 左:健常者、右:アルツハイマー患者)
スタディがスタートし、修道女たちの死亡に伴って脳の解剖が始まると、多くのケースは、アルツハイマー病が脳を破壊した証拠として脳の萎縮があり、健常者では1100グラムから1400グラムあるはずの脳の重量が、1000グラムに満たない状態でした。さらに、脳の表面の大脳皮質に刻まれたシワや溝にも変化が生じていました。
しかしながら、ナンスタディでは一般的なものとは異なる意外な症例も見つかったのです。いくつか同書から拾ってみましょう。
シスター・マリア(82歳死亡)
脳の重さが1160グラムあり、萎縮が強いわけではなく、神経原線維変化とプラークの数を数えると、ステージⅡに該当し、通常、プラーク分類でステージⅤ、あるいはⅥにならないとアルツハイマー病の症状が出ないっていうのが通説であったにも関わらず、シスター・マリアは生前に強い認知症の症状が出ていた。
知見☞ アルツハイマーの症状が軽くても認知症を発症したケース
シスター・マーガレット(91歳死亡)
脳の重量は970グラムしかなく、脳に通じる動脈にアテローム性動脈硬化が認められた。海馬に見られる神経原線維変化は90%に及び、プラークまでできていた。総合的に考えると、プラーク分類でステージⅤであったことから、もっと早期に認知症の症状が出ていても不思議ではなかったが、85歳までは認知能力に支障がなかったことが記録されている。
知見☞ アルツハイマーの症状が重くても、発症を抑え続けたケース
シスター・バーナデット
脳の重量は1020ミリグラム。ギリギリ正常の範囲。海馬と新皮質に神経原線維変化があり、それは前頭葉にまで及んでいた。新皮質にもプラークもたくさんできていて、プラーク分類でステージⅥであり、アルツハイマーが最も重い状態であった。しかしながら、心臓病でなくなるまで知的能力は全く正常であった。強靭な抵抗力。逃げおおせた人であったと言える。
知見☞ アルツハイマーの症状が重くても、発症しなかったケース
シスター・ローズ(100歳死亡)
脳の重さは1280グラムで、プラーク分類はステージ0だった。100歳で死ぬまで精神検査で高得点を維持し続けた。
知見☞ アルツハイマー病は高齢者が避けられない病気ではないことを物語るケース
認知症の発症は、必ずしも神経原線維変化とプラーク(アプロイドβ)の存在というアルツハイマー病の症状のレベルだけによるものではありません。
では、認知症の発症に影響がある他の因子は何なのでしょうか?
言葉とともに
同修道女会は誓願する(22歳の時)際に、半生記の提出を義務付けていました。その半生記は保管庫に全員分保管されていました。
その半生記は、200から300語程度で1枚の紙に、出生地、親の出自、子供時代の興味深く教訓的な出来事、通った学校、修道女を志したきっかけ、宗教、特筆すべき出来事を記します。
これを読み返すと、当時における修道女の人生に対するスタンスと語彙力を判定することができたのです。モーティマーとスノウドンは言語学者と協力して、修道女たちが22歳の時に書いた半生記を言語処理能力を表す意味密度と短期記憶に関連する文法的複雑さの2点から分析し、修道女たちの現状と比較を行いました。
その結果、数十年前に書かれた半生記の文章に見られる意味密度と現在の認知テストの間に、はっきりした相関関係を見つけたのです。
22歳の時に意味密度の高い半生記を書いた修道女は、高い認知能力を維持し続けることができたのです。モーティマーの言う、可塑性が強く柔軟な脳だったのです。
高齢になっても、認知症にならない修道女は、人生の早いうちから語彙が豊富で、子供の時にいろいろな種類の文章を読んでいたため、柔軟で強い脳がアルツハイマー病に対する抵抗力を有していたのですが、22歳のときに書いた半生記の意味密度の得点が低かったシスターは、既に何らかの形ですでに脳に障害が発生していたのではないかと考えられています。
では、子供にどうしてやればいいのでしょうか?
読み聞かですね。意味密度を左右するものは語彙力と読解力。語彙力と読解力を高めるには子供が小さいうちから本を読んで聞かせるのが一番。
脳は生涯を通じて変化し、成長続けるが、発達が最も著しいのはやはり生まれて間もない頃なので、誕生後、乳児期から幼児期にかけて、子供の脳は凄まじい勢いで成長していく。性的成熟が始まるずっと前から、脳の中では神経細胞同士の無数の接続が行われている。脳の発達には、その時々の経験が決定的な影響を及ぼす。つまり私たちの努力次第で、子供の脳の最大の力を引っ張り上げ、方向を決めることが可能になると言うことだ。
脳卒中(ラクナ梗塞)の影響
ナンスタディは意味密度に加えて、アルツハイマー病と脳卒中の相互作用が認知症を招くことを証明しました。
アルツハイマー病と診断できるだけのプラーク(アミロイドβ)及び神経原線維変化が同時に起こっている場合に、ラクナ梗塞と言われる小さな梗塞が1つでもあると、93%の修道女が認知症になっているのに対して、同じ状況であったとしても、ラクナ梗塞が全くない場合には、認知症の発生率は57%に過ぎなかったのです。小さな脳梗塞であるラグナ梗塞の有無が認知症の発症に大きく影響することが明らかになりました。
アルツハイマー病と脳卒中の相互作用
脳の解剖を行った結果(脳の解剖数 241)
認知症と診断された修道女 118名
そのうち アルツハイマー病だけ 43.0%
アルツハイマー病+脳卒中 34.0%
脳卒中だけ 2.5%
その他の原因 20.5%
アルツハイマー病が進行した脳に小さな梗塞が起きると、それがスイッチの役目を果たして、認知症の様々な症状が現れます。逆に梗塞を経験していない脳は、アルツハイマー病による損傷をある程度修復しながら、症状を抑えることができるのです。
プラーク(アミロイドβ)及び神経原線維変化の予防法はいまだに解明されていませんが、認知症になりたくなければ、できることからはじめましょう。
まずは脳卒中を予防することです。
脳卒中のリスクを減らす
脳卒中は脳の血管が破れるか詰まるかして、脳に血液が届かなくなり、脳の神経細胞が障害される病気で、以下の4つに分類されます。
(1)脳梗塞(脳の血管が詰まる)
(2)脳出血(血管が破れる)
(3)くも膜下出血(動脈瘤が破れる)
(4)一過性脳虚血発作(TIA)(脳梗塞の症状が短時間で消失する)
認知症予防
脳卒中の5大危険因子は以下の通りです。該当するものがあるでしょうか?
1.高血圧(血圧が140/90mmHg以上)
2.糖尿病
3.脂質異常症
4.不整脈(心房細動)
5.喫煙
最後に
大腸がんで101歳で亡くなったシスター・メアリーの死亡時の体重はわずか32キロ、脳の重さは870グラムしかなく、神経原線維変化は平均の3倍ありましたが、101歳まで正常な認知機能を保ちました。彼女の脳に梗塞はひとつもありませんでした。
シスター・メアリーのケースはアルツハイマー病を発症していても、認知症になるとは限らないことを語っています。特に梗塞がなかったことがその原因ではないかとされています。
認知症は予防できます。幼児の頃から可塑性のある強い脳を育てるとともに、脳卒中の予防に生活習慣を見直すことです。
認知症は、死の前の人生の総決算と言えるかもしれません。
認知症の発症に対する予防に加えて、認知症になってしまった際の備えとして 任意後見制度と意思能力喪失へ備えについてご案内しています。興味のある人は下のリンクから。
認知症のリスクはどこにあるのか?
・認知症の原因の約50%以上を占めるアルツハイマー病の原因と考えられている脳内の神経原線維変化とアミロイドβの蓄積は、若年時からすでに始まっていて、症状が出るまでに長い時間がかかる。
・意味密度が高い強い脳は基礎体力がしっかりしているので、アルツハイマー病になって組織がやられても、症状が出にくい。それには弱年時からの読み聞かせが有効
・アルツハイマー病が進行していても必ずしも認知症を発症するとは限らない。しかし、脳梗塞の発生はアルツハイマー病と相まって認知症の発症のスイッチとなるため、脳卒中の予防が認知症の予防に繋がる。
100歳の美しい脳 普及版 ~アルツハイマー病解明に手をさしのべた修道女たち~
デヴィッド・スノウドン 著、藤井留美 訳
出版社 : ディーエイチシー
<オンデマンドのオンラインスクール>
「リスクポリシーとしての公正証書5点セット」2,200円